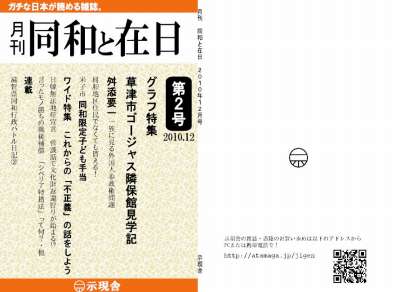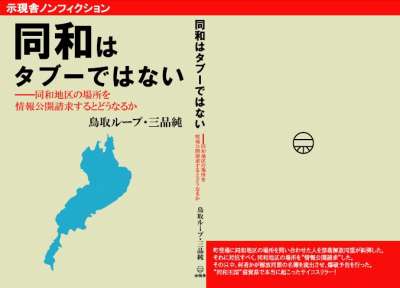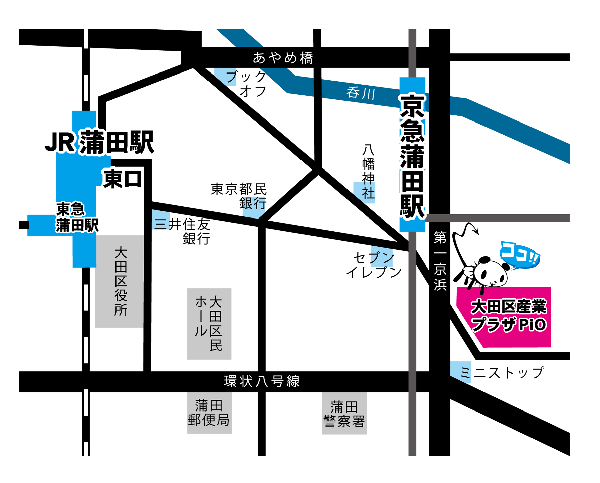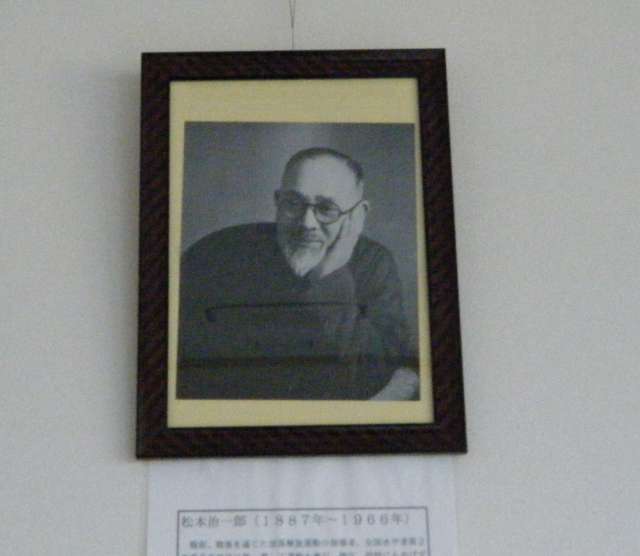ガチな日本が読める雑誌「同和と在日」第3弾。
被差別部落出身を明かしたタレント村崎太郎氏の故郷からの現地ルポ、知る人ぞ知る横須賀の同和住宅の謎を追うドキュメント 他
お買い求めはこちらから。
http://atamaga.jp/dz3
http://p.booklog.jp/book/17238
目次
●現地ルポ “プロ同和”村崎太郎が語らざる共産党・人権連の不都合な関係
・これがほとんどノンフィクション!?
・村崎節炸裂! 松本人志は九九ができない
・著書ではふれられない共産党一家
・村崎家のふるさとを訪ねて
・未償還金6億円! 光市の同和行政の影
・部落差別以上のアカという差別
・参考資料・村崎太郎氏の事務所の回答全文(原文ママ)
●神奈川県の同和史&事件簿
・同和をかたって福祉施設に温泉水を販売
・同和対策特別融資を悪用した県内最大の不祥事
●横須賀市―同和地区が消えた街に残された同和住宅
・地域改善向住宅
・横須賀の部落解放運動が遺した物
・市営住宅の“裏メニュー”
・「一般棟」と「同和棟」
・横須賀市民の財産
●同和にああ言われたら、こう言い返せ!
・「自分は被差別の立場で、あなたは差別する側だ」
・「今でも就職や結婚などで根強い差別が存在する」
・「○○は差別だ!」
・「寝た子を起こすなで差別はなくならない」
●滋賀県同和行政バトル日記③
・滋賀県の本気
・法務局から部落地名総鑑が開示される!?