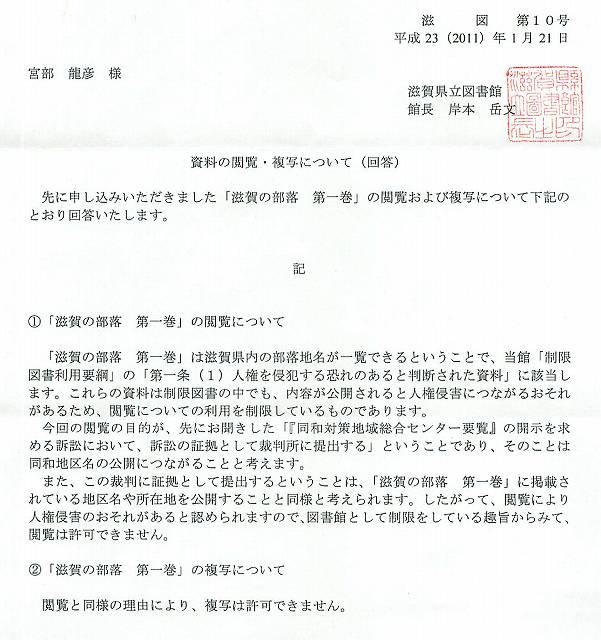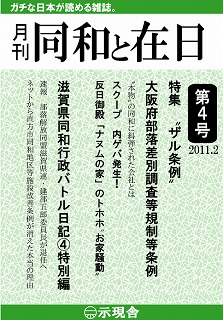本日、地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の第2回口頭弁論が行われました。
今回から法廷の様子をメモしましたので、克明にレポートします。
傍聴者は6人ほど、そのうちほとんどは県の職員のようでした。1人は鳥取ループのファンです。
最初は双方の提出した書類の確認です。双方が提出した準備書面、証拠書類について、手続上の問題等がないことが確認されました。
以降、裁判官が県側の弁護士を一方的に詰問するという展開となりました。おおよそ次のようなやりとりです。
裁判官「非開示情報について確認します。施設(同和対策地域総合センター)所在地は何丁目何番地何号まで書かれているのですか?」
県「そうです」
裁判官「ここは、細かな議論が必要なので、被告の方で整理していただきたいです。(同和)地区名とは具体的に何ですか?」
県「大字名または小字名です」
裁判官「施設名は全て所在地と関連性があるものなのですか?」
県「全てがそうではありません」
裁判官「その点、細かく整理してください」
裁判では、地域総合センターの施設名、所在地、同和地区名が個人情報かどうかが争点となっているので、個人が識別できるほどに具体的なものかということが重要になります。裁判官はそのことについて1つ1つの施設について検証して欲しいということのようです。
裁判官は被告の準備書面について、同和について長々と解説してあるが、核心部分の法律論について説明が足りない、というような感想を述べておりました。確かに、常識的に考えればそういうことになるのだと思います。
次に、情報が滋賀県情報公開条例第6条1項に該当するかどうかの検証です。つまり、地域総合センターの名称と位置、同和地区名が「個人に関する情報」または「個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当するかどうかです。ここで、いきなり裁判官が核心を突きます。
裁判官「具体例として、公営住宅の名称と位置が明らかになると、そこに住んでいる住人が住所から分かりますよね。これも条例第6条1項に該当することになるのですか」
県「…そういうことも、あると思います」
私が準備書面で「草津にある同和向け公営住宅の住人を調べれば、誰が同和関係者が分るじゃないか」という趣旨のことを書いたのを意識してか分りませんが、非常によい突っ込みです。
裁判官「例えば団地名と所在地で識別できるのは、そこに住む人全員であって、あるグループとしての人になるので、個人ではないのではないか。そういうことを議論してほしい」
さらに、「個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」についても裁判官は突っ込みます。
裁判官「情報公開法では、例えば「未発表の著作物を公開してしまうと、誰が権利者か分らなくても人の権利を侵害することになる」「カルテのように、誰のものか分らなくても病歴などの情報が本人の知らないところで流通する」ということを想定しています。立法趣旨からするとそういうことではないですか」
つまり、どう考えても「1人の人間」とは結び付けられない同和地区という情報を、個人の権利を害すると解釈することを、情報公開法は想定していないということです。
県「これは県の条例ですから…」
裁判官「書いてあることは国の法律とおなじことでしょ」
ここまで述べられたことに加えて、滋賀県情報公開条例第6条6項つまり県の事務事業に支障を生ずるような情報であるかどうかも、もっと法律的な議論を整理するように県に宿題が出されました。
県の準備書面提出期限は3月18日です。
そして、次回口頭弁論は4月21日13時10分に設定されました。
まだまだ裁判は続きます。